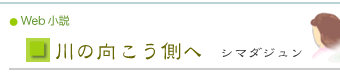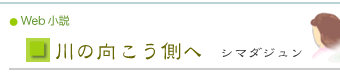|
寺岡よしえは僕の手を取って立ち上がろうとしたが、何かの調子で身体のバランスを崩した。
僕の腕が思いっきり地面の方へと引っ張られた。僕もバランスを崩してしまい、なんとか脚に力を入れ踏んばり、彼女を支えようとしたがダメであった。
僕たちは重なり合うように地面に倒された。
僕は身体を斜めにねじるようにしたため、何とか彼女の上に覆いかぶさるようにはならなかったが、偶然に脚が絡み合うような形になってしまった。
僕はすぐに立たねばという思いを曳きずりながらも、このままでいたいという衝動も同時に僕のこころに拡がった。僕はうつ伏せのまま顔を横に向けた。寺岡よしえは立ち上がろうともせず仰向けになったまま、同じように顔を横に向け僕の眼に自分の視線を絡ませた。
彼女は微笑んでいた。
立ち上がる意志はないように感じられた。言葉もなく、彼女の右手が僕の脇に添えられ強い力が加わった。
僕はその意味を考えたが、よくわからないままジッとしていると、彼女の右手が動き何度か僕の髪をまさぐった後、首に回って同じように力が加わった。僕はようやくその意味がわかったが、どうすることもなくジッとしていた。
「ユウちゃん。大丈夫だから……私ずっとユウちゃんのことみているからね。樋上さんの事はなんの心配もしなくていいよ。ユウちゃんは自分のことだけ考えていればいいから……さあ、行こうか」
そう僕の耳元でささやくと、彼女は乱れていたスカートの裾を直し、膝を立てながら立ち上がった。
「さあ、ユウちゃん行こう……」
半身になって地面に伏している僕を見下ろしながら言った。
どうしようもないような彼女の笑みが僕を捉えた。自信に満ちた優しさがあふれ返り、僕を吸い込んでしまいそうな表情であった。
どうしてだろう?僕は逃げ出したくなった。その想いを必死に押さえながら、僕も立ち上がった。果たして、僕はどんな表情を顔に浮かべていたのだろうか?想像も出来なかった。そして、置き場のない恥ずかしさのためか、自分の感情をうまくまとめ切る事が出来ず、ただ呆然と立ち尽く事しか出来なかった。
死の方向へひたすら進もうとしている樋上通子を何とか救済しようとしても、僕はその方法を見いだすことが出来なかった。
「無理です。僕には何も出来ません」そう言ってその緊張感が張りつめている保護室から立ち去ってしまいたかった。
もう、限界であり、僕にはその、人一人の生命がかかっている危険な事態を突破していく力などありそうにもなかった。
でも、主治医と看護婦の寺岡よしえの僕に対する期待を簡単には裏切れない気持ちは、僕の内からは簡単には消えては行かなかった。事実、彼らの力でその状況を打開出来ないことは僕は理解していた。だからこそ、余計に苦しかった。僕は、僕の目の前で一人の人間の命が消えかかろうとしている現実が怖かった。自分の非力を恨んだ。
その瞬間どうしようとする意志の形もないまま、僕は何かに惹かれて行くように、ふらふらっと、依然として刃物を自分に向けている樋上通子の方へと近づいていった。
それは、何の意図もない行動であった。もうどうなってもいいという投げやりなものが僕を捉え始めていたのかも知れない。
「ユウちゃん。しっかり」寺岡よしえの声が聞こえたような気がしたが、僕は振り返ることも、その言葉に応えることもなく樋上通
子に歩み寄って行った。いや、その激励の言葉さえ僕が勝手に創り出した幻想であったかも知れない。
僕は完全に無策であった。樋上通子を救済しようとする意識とは違った世界を泳ぎ始めていた。
その苦しい、息がつまりそうな状況にもう耐えられず、終止符を打ってしまいたい気だけであったように思える。
「いや。こっちに来ないで!」
樋上通子の激しい拒絶が聞こえたような気がしたが、その言葉は僕の中で、きちんとした像を結ばなかった。
僕は何を見つめるということもなく、何をしようとする気もなくただ彼女に近づいて行った。
「それ以上来たら、刺すわよ」樋上通子が叫んだ。
(刺す?……誰を?僕を?それとも自分を?好きにしたらいい……)僕はもうためらうこともなかった。
「ユウちゃん……しっかり」再び寺岡よしえの声が微かに聞こえたような気がした。
気がつくと、僕は樋上通子のすぐ側にいた。
僕はなんの計算もせずにひざまづいた格好で言った。
「死にたかったら、死ねばいいだろう。誰の人生でもなく樋上さんの人生なんだから。激励でも説得でもないけどね、死のうと思ったらいつでも出来るんじゃあないの。僕はそれが今だとは思わない。でも、そんなに死にたかったら僕は止めやしないよ。さあ、そんなに生きていくのが怖かったら、死ねばいい」
僕はゆっくりと刃物を持っている彼女に手に僕の右手を重ねた。
樋上通子は激しく震えていた。その振動が僕の手から身体全体に伝わってきた。その刃物を持っている樋上通子の手は僕の方にも、彼女の方にも力が加わる事なく静止したままであった。僕は動揺する事もなく、彼女の手からその刃物を難なく抜き取り、保護室の入り口の方に向かって地を這うように投げた。
「樋上さん。さあ、ベッドでゆっくり休もう。僕ら仲間じゃあないか。なんの心配も入らないから。さあ、ゆっくり立って」
何を意味していたのだろう。樋上通子は声を立てることもなく、黙ったまま泣いていた。素直で汚れのない涙であった。
僕は、そっと彼女の頬に流れている涙を手で拭いた。
「さあ、立って。一緒に向こうへ行こう」
寺岡よしえがその時、ゆっくりと進んで来て樋上通子を抱きしめた。
「樋上さん。よく頑張ったね。でも、もういいから。私、なにもしたあげられなくてごめんね」
寺岡よしえのその言葉は涙声であった。
「ユウちゃんありがとう。本当にありがとう。どうお礼を言えばいいのか……」
寺岡よしえは今にも泣き出しそうになるのを必死にこらえていたのが僕にも伝わってきた。
僕は依然として、上の空のような気分であった。誰かを助けたというよりも、我慢が出来ない程の緊張が通り過ぎたことが嬉しかっただけであった。
寺岡よしえにも声をかけることもなく、じっとその場に立ち続けていた……
|